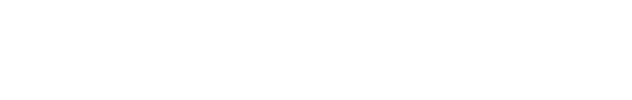階層から検索する
階層から検索する所蔵資料を省庁別等に「資料群」としてまとめました。
資料群 → 簿冊 → 件名の階層構造や概要が分かります。
検索条件 : 復員局資料整理部
絞り込み検索
アジ歴グロッサリー内検索【 グロッサリー内検索について 】
アジ歴グロッサリーでサイト内検索を行います。
※アジ歴グロッサリーとは
アジ歴で資料を検索する際のテーマ別歴史資料検索ナビです。テーマ別にキーワード一覧、地図、組織変遷表、年表等から、お探しの資料や関連資料にスムーズにアクセスすることができます。
< 現在公開中のテーマ >
・公文書に見る終戦 -復員・引揚の記録-
・公文書に見る戦時と戦後 -統治機構の変転-
・公文書に見る外地と内地 -旧植民地・占領地をめぐる人的還流-
・公文書にみる明治日本のアジア関与 -対外インフラと外政ネットワーク-
- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]C19100090400
閲覧[規模]6
- [所蔵館における請求番号]濠北-ボルネオ-54(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]一九四五年春頃に於けるボルネオ地区及びタラカン島陸軍兵力調査に関する件 一九四九年九月十三日 復員局資料整理部 首題の件左の通り報告する 地域 時期 説明 一、本調査は左記資料を基礎として実施したものである 左記 (イ)復員局留守業務部保管留守名簿 (ロ)復員局留守業務部保管第三十七軍各部隊人員調査表 (ハ)復員局留守業務部保管第三十七軍部隊行動概要 (ニ)復員局調製ボルネオ作戦記録第二巻 (ホ)元第三十七軍作戦参謀大佐高山彦一及同中佐岩橋学の記憶 (ヘ)復員局より当時の各部隊長(又は責任者)に連絡して得た資料 二、人員算定の経緯 A、一九四四年末ボルネオ兵備態勢が一応完成した時機に於けるボルネオ地区及タラカン島兵力及尓後終戦迄の損耗は次の通りである
- 作成年月日1949年9月13日
- 作成者復員局資料整理部
No.
[レファレンスコード]C15010050500
閲覧[規模]45
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-15(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]馬来攻略計画 一九五一、四、二八 復員局資料整理部 「註」 本攻略計画は元第二十五軍参謀中佐橋詰勇の所持する資料及復員局に於て編纂した左記作戦記録に拠り調製したもので之以上準備なる資料は現在求め得ない。左記 大本営統帥記録 南方軍作戦記録 馬来作戦記録 第二十五軍 南方全般航空作戦記録 馬来攻略計画 (一) 南方作戦の為大本営が立案した作戦計画中馬来に関聯する事項は次の如くである。大本営は一九四一年十一月十五日南方軍総司令官に南方作戦開始の準備命令を与へると共に本作戦計画に準拠する如く指示した。大本営作戦計画抜萃 一、戦争目的 南方作戦の目的は東亜に於ける米国、英国及南国の主要なる根拠を覆滅し南方要域を占領確保するに在り
- 作成年月日1951年4月28日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010051800
閲覧[規模]27
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-15(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]香港攻略作戦に就て日本側の見地よりする諸問題(所見、戦訓、考案等) 一、要塞等堅固なる施設を攻略するに決心した場合は、攻略するに十分なる兵力と準備時日の余裕、特に訓練精到で必勝の信念充実せる部隊を使用し短切なる打撃をして一挙に攻略する事が必要である。香港要塞は不十分な兵力、不十分な準備、特に不精な軍隊を以ては攻撃を繰り返し仮に長時日を以てするも中々取れるものではなかつたでなかろうか。此の点太平洋戦争始め香港の攻略は立派に計画せられたものであつて特に部隊の訓練精到であつた事は事実であれだけの要塞が一箇師団の兵力でよく攻略し得たと思はれる次第である。攻略後英軍ボクサー参謀の言に依ると約半年位は持久する考へであつたらしく、
- 作成年月日1951年7月1日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010052500
閲覧[規模]29
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-15(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]旧日本陸軍に於ける高射砲の指揮系統に関する報告 一九五一年九月 復員局資料整理部 註 本報告の作製に方りては作戦記録に拠るの外元大本営航空主任参謀田中耕二中佐、元航空総軍作戦主任総務佐藤勝雄中佐、元バレンバン防衛参謀松元泰清大佐を招致会同研究を行つた。一、前言 旧日本陸軍に於て高射砲は地上部隊に属していた。即ち之は砲兵から発達したものであつて其の教育、補充、人事等は砲兵の一分科として取扱れて来た。従つて高射砲は其の本然の性格上地上部隊よりも航空部隊とより緊密なる関聯性を持つべきに拘らず原則として地上軍の指揮下に於て作戦する伝統に支配せられてゐた。かくて旧日本軍に於ては高射砲を航空軍の作戦指揮下に置いた場合
- 作成年月日1951年9月
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C14110546600
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]南西-マレー・ジャワ-6(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]馬来攻撃計画 昭二六、四、二八 資料整理部
- 作成年月日昭和26年4月28日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C14110546700
閲覧[規模]3
- [所蔵館における請求番号]南西-マレー・ジャワ-6(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]馬来攻略計画 昭和二十六年四月二十八日 復員局資料整理部 馬来攻略計画 一九五一、四、二八 復員局資料整理部 「註」 本政略計画は元第二十五軍参謀中佐橋詰勇の所持する資料及復員局に於て編纂した左記作戦記録に拠り調製したもので之以上詳細なる資料は現在求め得ない。 左記 大本営統帥記録 南方軍作戦記録 馬来作戦記録 第二十五軍 南方全船航空作戦記録
- 作成年月日昭和26年4月28日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C14110546800
閲覧件名馬来攻略計画
[規模]3
- [所蔵館における請求番号]南西-マレー・ジャワ-6(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]馬来攻略計画 (一) 南方作戦の為大本営が立案した作戦計画中馬来に関聯する事項は次の如くである。 大本営は一九四一年十一月十五日南方軍総司令官に南方作戦開始の準備命令を与へると共に本作戦計画に準拠する如く指示した。 大本営作戦計画抜卒 一、戦争目的 南方作戦の目的は東亜に於ける米国、英国及蘭国の主要なる根拠を覆滅し南方要域を占領確保するに在り 二、作戦方針 南方軍は聯合聯隊と協同し比律賓及英領馬来に対し同時に作戦を開始し努めて短期間に作戦目的を完遂す 三、作戦指揮要領 馬来に対する先遺兵団の上陸並比律賓に対する空襲を以て作戦を開始し航空作戦の成果を利用して各攻略兵団の主力を以て先つ比律賓に次で馬来に上陸せしめ
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C16120091300
閲覧[規模]18
- [所蔵館における請求番号]陸空-比島(決戦)-22(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]其一(飛行部隊)比島ニ進出シタ時期(年、月)部隊名比島カラ転出シタ時期(年、月)摘要一九四一、一二第五飛行集団司令部一九四二、一一九四一、一二第四飛行団司令部一九四二、一一九四一、一二飛行第五十戦隊一九四二、一一中隊ヲ比島ニ残置一九四一、一二飛行第八戦隊一九四二、一一九四一、一二飛行第十六戦隊一九四二、七一九四一、一二 一九四四、一〇飛行第十四戦隊一九四二、一 一九四四、一一一九四一、一二 一九四四、五飛行第二十四戦隊一九四二、一 一九四四、一二一九四一、一二第十独立飛行隊本部 一九四三、四一九四一、一二独立飛行第五十二中隊終戦時「カガヤン」河谷一九四一、一二独立飛行第七十四中隊一九四三、四一九四一、一二独立飛行第七十六中隊
- 作成者復員局資料整理部
No.
[レファレンスコード]C13031937800
閲覧[規模]25
- [所蔵館における請求番号]支那-大東亜戦争全般-56(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]支那方面作戦記録第一巻中訂正事項 Monograph No.70 (Army) Errata Sheets for China Area Operations Record, Vol.1. Prepared by First Damobilization Bureau. May 49 訂正済 昭和二十四年五月調製 復員局資料整理部 註 一、訂正内容の区分 別冊其の一 実質的に英訳文に影響ある事項 別冊其の二 英訳文には殆ど影響なきも日本文として訂正を要する事項 二、点検担当者 点検主任者 元大本営陸軍参謀、支那派遣軍参謀、南方軍参謀、第二方面軍参謀、第五航空軍参謀副長 元大佐堀場一雄 点検参加者 元大本営陸軍作戦課長 元大佐服部卓四郎 元陸軍省軍事課長、支那派遣軍参謀 元大佐西浦進 元大本営陸軍参謀、第十四軍参謀、航空総監部課長、支那派遣軍参謀 元大佐秋山紋次郎
- 作成年月日昭和24年5月
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C14060507600
閲覧[規模]7
- [所蔵館における請求番号]南西-泰仏印-43(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]仏領印度支那方面作戦記録中訂正事項 Monograph No. 25 (Army) Errata Sheeta for French Indo-China Area Operations Record. Prepered by first Demobilization Bureaau. May 49 昭和二十四年五月調製 復員局資料整理部 註 一、訂正内容の区分 別冊其の一 実質的に英訳文に影響ある事る事項 別冊其の二 英訳文には殆ど影響なきも日本註として訂正を要する事項 二、点検担堂り者 点検主任者 元南方軍参謀、第二総軍参謀 元少佐 山口二三 点検参加者 元大本営陸軍作戦課長 元大佐 服部卓四郎 元陸軍省軍事課長、支那派遣軍参謀 元大佐 西浦進 元南方軍参謀、第二方面軍参謀、第五航空軍参謀副長
- 作成年月日昭和24年5月
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C14060803800
閲覧[規模]3
- [所蔵館における請求番号]南西-軍政-163(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]昭和二十六、四 馬来攻略計画 復員局資料整理部 馬来攻略計画 昭和二十六年四月二十八日 復員局資料整理部 部長 馬来攻略計画 一九五一、四、二八 復員局資料整理部
- 作成年月日昭和26年4月28日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省 防衛研修所戦史室
No.
[レファレンスコード]C14020717400
閲覧[規模]3
- [所蔵館における請求番号]比島-全般-140(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]比島第一期作戦兵力表 昭和二三、九、一〇 青島元大佐起案 昭和和二四、五、二三 杉田元大佐修正 昭和二四、六、九 杉田秋山元大佐再修正 復員局資料整理部 (表) 部隊名 兵力 摘要 第十四軍司令部 軍直部隊 兵站部隊 第四師団 第五師団ノ一部 第十六師団 第十八師団ノ一部 第二十一師団ノ一部 第四十八師団12963 第五十六師団ノ一部 第六十五旅団 合計 外ニ補充員 総計 [(表)以下省略] 考備 一、本表諸元ノ基礎左ノ如シ 1、主トシテ昭和二十一年三月十五日第一復員局調製年度別動員兵力一覧表並基ノ原本(起案者元少佐斉藤春義)ニ拠ル 2、極メテ一部ノ部隊ニシヲ拠ルヘキ記録ヲ発見シ得サリシモノハ同種類ノ部隊ヨリ類推ス
- 作成年月日昭和23年9月10日~昭和24年6月9日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010230500
閲覧[規模]3
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-365(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]昭和九~二〇年 満洲に関する用兵的観察 第九巻 第四篇 満洲に於ける各種作戦の史的観察 第五章 冬季作戦 満洲に関する用兵的観察 第九巻 第四篇 満洲に於ける各種作戦の史的観察 第五章 冬季作戦 昭和二十七年九月 復員局資料整理部 関東軍司令部 (ノモンハン研究委員) 一九三九年 中佐 工兵第十一聯隊長(虎林駐) 一九四〇年 一九四一年 大佐 岡田元治 大本営参謀 一九三六年 一九三九年 大尉少佐 関東軍参謀 一九三九年 一九四年 中佐 関東一軍参謀 一九三九年 一九四〇年 少佐 第一方面参謀 一九四三年 大佐 島貫武治
- 作成年月日昭和27年9月
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010037800
閲覧[規模]7
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-13(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]比島作戦第一期日本軍兵力表に対する意見 昭和二十四年七月二日 復員局資料整理部 本作業は航空部隊の大部を当時の現員表に拠り其他は定員表に拠り算出してあるが現存資料で能ふ限り近似値を算定する方法としては@し妥当である但し定員表に予つたものは動員@不@の傷痢事故等に依り或は極めて少数の欠員が生し又は定員外の兵員を同行した場合もあることを念頭に置く必要があるが之等を加@すへき資料は無い 作製は一般に正確であり大なる釤陥は認るられないが一@適確を@するため以下述ある知き修正乃全解釈を応すことが通常である 一、(名称) 第五十六師団の一部は混成第五十六歩兵団と其の名称を@@する (出所) 資料の出所を左の如く修正する
- 作成年月日1949年6月20日~昭和24年7月2日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010038400
閲覧[規模]12
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-13(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]一九四五年春頃に於けるニユーブリテン島、ニユーアイルランド島、ボーゲンビル島及ニユーギニヤ日本陸軍の地域別人員に関する件 一九四九年七月三十日 復員局資料整理部 首題の件調査の結果左表の通り報告する。尚ボルネオ及タラカンの人員は尚調査中にして調査完了次第報告する。(表) 期日 地域 ニユーブリテン ニユーアイルランド ボーゲンビル ニユーギニヤ 三月 四月 五月 六月 [(表)以下省略] 備考 一、各月末現在の人員を示す 二、ニユーアイルランドの人員は一位の人員を四捨五入した概数である。誤差は一〇名以内と認める。三、ボーゲンビル及ニユーギニヤの人員は一〇位以下を四捨五入した概数である。誤差は一〇〇名内外以下と認める 四、ニユーギニヤの人員は当ウエワク周辺地域に其全力
- 作成年月日1949年7月30日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010040100
閲覧[規模]6
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-13(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]一九四五年春頃に於けるボルネオ地区及タラカン島陸軍兵力調査に関する件追加 一九四九年九月二十日 復員局資料整理部 首題の件に関し一九四五年九月十三日附報告したボルネオ地区人員に左の通り陸軍航空部隊人員を追加する 従てボルネオ地区陸軍兵力は下段記載の如くなる (表) 時期 区分 陸軍航空部隊兵力 ボルネオ地区全陸軍兵力 三月 四月 五月 六月 [(表)以下省略] 備考 一、各月末現在の人員を示す 二、本表人員には第三航空軍及第四航空軍よりボルネオに派遣して居た通信、気象、航測、修理補給部隊の各一部の推定人員合計一、八〇〇名を含む 説明 一、本表航空部隊の兵力調査は左記資料を基礎として実施したものである 左記
- 作成年月日1949年9月20日
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010002200
閲覧[規模]12
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-3(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第三篇 満洲に対する戦略戦術的兵要地理観察 総目次 (起案者) 上巻 第一章 総説 (堀場一雄) 第一節 史的観察 一-一 第二節 潜在戦力 一-四 第三節 満洲の基本的地位 一-七 第二章 戦略的一舳観察 第一節 綜合観察 (堀場一雄) 二-一 第二節 地上作戦 二-六 第一款 鉄道 (河村弁治) 二-六 第二款 道路 (今岡豊) 二-一七 第三節 航空作戦 (下山琢磨)_第一款 戦略的観察 二-二九 第二款 飛行場 二-三三 第三款 気象 二-三七 第四節 上陸作戦 (纓井省三) 第一款 戦略的観察 二-四一 第二款 港湾、海岸 二-四二 第五節 補給 (今岡豊) 第一款 物資 二-四八 第二款 輸送機関 二-五七
- 作成年月日昭和27年3月
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010002300
閲覧[規模]18
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-3(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第三篇 満洲に対する戦略戦術的兵要地理観察 第一章 総説 第一節 史的観察 一、興亡概観 満洲の原住民には三千年の歴史があり就中顕著なる建国をなしたものには資金(元)清等がある 今之を兵要地理の参考として興亡の跡を辿れば次の如くである 1.粛慎、扶余、粛慎は三千年前中国周秦の時代、史上最初に視れた原住民である 穢、貊族と共に遂さ満に居住し(粛慎は北満東部、穢貊は北満平野)独特の文化を持ち約十世紀を閲した 貊族は後その中心地の名称を冠して扶余族と称した 2.高勾龍 高勾麗族は鴫緑江上流扶余族より出でその文化を継承し通化省を本拠として南満及北鮮を領域とし前三七年より前六六八年即二十八代七百五十年に亘り存在した
- 作成年月日昭和27年3月
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010002600
閲覧[規模]48
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-3(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第三節 航空作戦 第一款 戦略的観察(附図第五参照) 日本諸島に対し千島、南樺太、東部沿海州、満洲(北鮮を含む)、山東、江蘇を連ねる線は両端に於て包囲し中央に於て略々並行的に位置し現代軍用飛行機に対しては約一時間半内外の行動半径内に在つて攻略の為正に恰適の航空基地線を提供せるものと謂はねばならぬ 特に従来蘇側は専ら満洲東部方面よりする日本軍の攻撃に対応するのを主にして東部沿海州就中烏蘇里、タウビエ河谷に航空兵力の主体を配置して居つたものゝ如くであるか今や此東西に薄く南北に厚い配置を一変して日本島に向つて平行的に横広い展開たなし殊に比較的気温緩和にして労力物資の豊冨な満洲に基地のため縦深広大な地域を得るに
- 作成年月日昭和27年3月
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010002900
閲覧[規模]36
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-3(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第四章 北満平野 第一節 位置及区域 北満平野と云へば一般通念として新京以北安以南のハルビン、チ、ハル等を含んだ地域を総称するも本章に於ては概ね東経一二三度乃至一二九度、北緯四三度乃至四七度の間て吉林省及浜江省の区域とする本地域の位置は略々満洲の中央部に位し松株式会社公江流域の大平野であつて東は間島省、牡丹江省、三江省に接しなさは北安省西は龍江省南は通化省、奉天省に境を接している 第二節 戦略的観察 第一款 本地域の戦略的価値 其の一 地形上より見たる戦略価値 一、本地域は満洲の略中央に位の地形は大部分が平地で交通の中心をなし、東西南北各地域よりの交通幹線は本地域に集中し満洲に於ける政戦両略上の重要地域である
- 作成年月日昭和27年3月
- 作成者復員局資料整理部
- 組織歴陸軍省