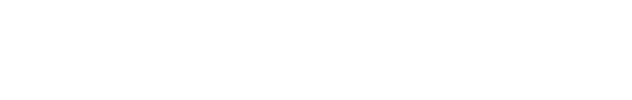階層から検索する
階層から検索する所蔵資料を省庁別等に「資料群」としてまとめました。
資料群 → 簿冊 → 件名の階層構造や概要が分かります。
検索条件 : 復員局資料整理課
絞り込み検索
アジ歴グロッサリー内検索【 グロッサリー内検索について 】
アジ歴グロッサリーでサイト内検索を行います。
※アジ歴グロッサリーとは
アジ歴で資料を検索する際のテーマ別歴史資料検索ナビです。テーマ別にキーワード一覧、地図、組織変遷表、年表等から、お探しの資料や関連資料にスムーズにアクセスすることができます。
< 現在公開中のテーマ >
・公文書に見る終戦 -復員・引揚の記録-
・公文書に見る戦時と戦後 -統治機構の変転-
・公文書に見る外地と内地 -旧植民地・占領地をめぐる人的還流-
・公文書にみる明治日本のアジア関与 -対外インフラと外政ネットワーク-
- No.
- レファレンスコード
- 概要
No.
[レファレンスコード]C14060243400
閲覧[規模]3
- [所蔵館における請求番号]南西-ビルマ-188(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]昭和二〇、一、下~二一、六、二五 独立混成第七十二旅団戦史資料 復員局資料整理課
- 作成年月日昭和20年1月~昭和21年6月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省 防衛研修所戦史部
No.
[レファレンスコード]C13010009500
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-9(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]目次 (執筆者) 頁 第一節 湿地 (不破博) 一 第一款 満洲に於ける湿地の地形的特性 三 第二款 満洲に於ける湿地の作戦的特性 七 第三款 湿地帯を通して行ふ攻勢作戦に対する観察 一三 第四款 湿地帯を前にする防勢作戦に対する観察 二五 第二節 河川 第一款 満洲河川の特性 三〇 第二款 黒龍江の渡河作戦 (板垣徹) 三三 第三款 ノモンハン事件に於けるハルハ河の渡河作戦 (村沢一雄) 四三 第三節 広漠地 (島貫武治) 四六 第一款 広漠地の特性 四六 第二款 広漠地作戦の戦例 四八 第三款 広漠地作戦の戦略観察 第四款 広漠地作戦の戦術的観察 第五款 ノモンハン事件に参加した一参加の広漠地戦@に関する教訓
- 作成年月日昭和27年8月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010009800
閲覧[規模]39
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-9(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第二節 河川 第一款 満洲河川の特性 満洲の河川は黒龍江及公公江に依つて代表せられる北満の大河と平原地帯を蛇行する河川用及山間の小河川とに大別せられる。而して山間の河川は河川の一般概念同様のもので取り立てる程の特徴はないが平原地帯の河川と北満の大河には特異の性格がある。其の一 平原地帯の河川の特性 一、蛇行分流し流速極めて緩慢である。満洲平原地帯の河川は極度に蛇行して流れ其の延長距離は直距離の少くも五倍以上に達し且其の流線は数条に分れ毎年解氷後の氾濫に依り河床の変更を来すを通常とする。勿論速は甚だ緩慢であり連常秒達数十種以下である。従つて作戦上河川を交通線として利用することは其の価値少く不適当である。
- 作成年月日昭和27年8月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010009900
閲覧[規模]53
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-9(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第三節 広漠地(@) 第一款 広漠地の特性 満洲内に於て広漠地を求むれはハルビン、チ、ハル中間の安達附近、熱河省北端から興安西、南省に亘る間及海拉爾附近ホロンバイル高原等を挙げることが出来るが満洲の作戦に密接な関係を有する内蒙、外蒙は其の広さ日本海にも匹敵すべき広漠地である。即ち見渡す隈りの大高原で殆んど山もなく森もなく住民地もない草原又は砂漠状態の高原でゴビ砂漠が其の西方に連なる。草原には蒙古人遊牧を行い稀に大蒙古時代の寺院を見る。昔忽必烈の卒いた蒙古軍は欧洲迄遠征し之を其の支配下に服させたこともあるが今や人口極めて稀薄であつて文化著しく我く牧畜の他産物なく所謂不毛の地であつて太陽は地平線から出でゝ地平線に没し陸の海原とも称すべき地域でる。
- 作成年月日昭和27年8月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010010000
閲覧[規模]43
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-9(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第四節 山地及森林(@) (注一九)満洲に於ける山地と森林とは不可分のものである。即ち満洲の山地特に東正面の山地は概して森林に依つて蔽はれ又満洲に於て森林のある所は殆ど山地である。従つて満洲に関する用兵的観察に方りては両者を同時に取扱ふのが適当である。本節に於て億先づ満洲に於ける山地と森林との特性を個々に観察し次で東正面の森林に蔽はれた山地帯に於ける日本軍の作戦的体験を記述する。第一款 満洲に於ける山地及森林の特性(20) (注二〇) 本款は関東軍参謀並に満洲東正面の作戦を担任した第三軍高級参謀及第二十軍参謀長等を歴任した元陸軍少将中@頁武の体験に基く記録である。同少将の軍歴の概要は次の通のである。
- 作成年月日昭和27年8月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010057600
閲覧[規模]4
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-16(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]一九五二年七月に於ける戦史関係業務通報の件 一九五二年、七、三一 復員局資料整理課 一、作戦記録の編纂 「南支那方面作戦記録 第一巻」の編纂を完了した。 二、G-2よりの依頼により調査した事項 1.「満洲に関する用兵的観察」に就いて 一、「満洲に関する用兵的観察 第二巻」の編纂を完了した。 一、前項以外の記録の調製、審議及編纂の為の資料を収集整理した。 2.其の他の調査 一、航測隊の性能に関する件。 一、特種情報部拡充強化し目次に就いて。 一、印度カルカツタ攻撃発起の経緯及中止の事情に就いて。 一、緬甸に於ける日本軍飛行機の性能に就いて。 一、第三十七師団の第三十八軍隷属転移のまま次に就いて。
- 作成年月日1952年7月31日
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010057800
閲覧[規模]1
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-16(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]一復資整庶第一三号 レイテ作戦増援部隊の海没損耗調査の件依頼 昭和二十七年八月一日 復員局資料整理課 留守業務部 御中 レイテ作戦の為比島各地(呂宋島、ミンダナオ島等其他)よりレイテ島に増強せられたる部隊の海没による損耗に就いて左記調査の上成る可く速かに回答煩し度依頼する。 左記 一、単位部隊毎の海没損耗(人員及主要兵器) 二、海没の時期及場所
- 作成年月日昭和27年8月1日
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C15010058400
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]中央-終戦処理-16(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]一九五二年八月に於ける戦史関係業務通報の件 一九五二、八、三一 復員局資料整理課 一、記録の編纂 「満洲に関する用兵的観察」に就いて 1.「満洲に関する用兵的観察 第六巻、第七巻及第八巻」の編纂を完了した。 2.前項以外の記録の調製、審議及編纂の為の資料を収集整理した。 二、G-2よりの依頼により調査した事項 1.常徳作戦の作戦目的に就いて。 2.終戦時戦闘序列解除に関する大命発令に就いて。 3.カルカツタ爆撃の開始及終了の真相に就いて。 4.カルカツタ爆撃に於ける我軍の損害概要に就いて。 5.昭和十七年初頭に於ける在ビルマ各師団の部隊長の官氏我の調査。 6.インパール作戦中止の指導に関する件。 7.其の他電話連絡による主要なる調査 二件。
- 作成年月日1952年8月31日
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010004800
閲覧[規模]5
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-5(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第三節 一九四一年以降に於ける在満航空部隊の状況 資料提供者 元第二航空軍参謀中佐 佐藤勝雄 一、一九四一年六月独蘇開戦に伴い在満航空部隊は万一の事態に備へて応急警戒配置に就き次で応急動員を令せられ又内地より直協飛行隊飛行場大隊、飛行場設定隊、修理補給機関等を増加され更に空中勤務者及航空資材を補充された。此の事態を関東軍特別演習(関特演)と呼んた。関特演特期は在満航空部隊の最盛期であつて一九四一年十月頃に於ける飛行部隊兵力は八十二中隊(約八百四十機)であつた其の状況は附表第七に依る。二、一九四一年十一月南方作戦の開始に備へ第五飛行集団、第十二飛行団等の諸隊は拙出されて夫々台湾、仏印に転し在満航空部隊は此の時を峠として漸次減少するに至つた。
- 作成年月日昭和27年6月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010004900
閲覧[規模]6
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-5(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第四節 施設 第一款 飛行場 一、飛行場配置に関する観察 満洲の飛行場配置は其の作戦上の性質から三種類に分類するのが妥当てある。其の一は国境地帯に在る作戦実施の飛行場群で東正面に於ける佳木斯、牡丹江以東地区の飛行場西地区に於ける斉々哈爾以西の飛行場等大部分の飛行場は此の種類に関する其の二は此等の作戦実施飛行場群の後方@点とかり交東西北の作戦実施飛行場群間を機動する飛行部隊の為に機動@軸の役目を果す飛行場群て哈爾賓、新京附近に布置されたものかこれてある。航空部隊は此等の飛行場の主要かものに常駐した又機動@軸の役目の飛行場群には地上勤務施設が大規模に関するものは奉天附近に配置されたものでこれは満洲と内地、
- 作成年月日昭和27年6月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010005000
閲覧[規模]58
[種別]図
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-5(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第五節 気象 第一款 在満気象部隊の編制製備 資料提供者 元第二航空軍気象部長少佐荻洲博之 一、気象軍創設以来関東軍司令部及所要の師団司令部(兵要地誌班)に気象掛将校が居り満洲及蘇聯の兵要気象調査を担当していた。満洲国の建国に伴い中央観象台が満洲国気象機関として整備され更に一九三八年八月関東軍気象部が創設された。該部隊は平時に於ける兵要気象の研究調査を強化する目的を持つたものてあつて軍属を主として居た。一九四〇年三月関東軍気象部は関東軍気象隊と改編せられ従来の任務の外進攻作戦に応ずる軍気象観測綱の構成、放送の実施と云う任務を附加され兵員を主とする純然たる軍隊となつた。但し従来の軍属を主としたものは第二本部と云う名称の下に引続いて兵要気象の研究調査を行つていた。
- 作成年月日昭和17年
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010010600
閲覧[規模]6
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-10(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]目次 総説 第一節 冬季の作戦的特性 四頁 第一款 寒気 九頁 其の一 冬季及冬季に於ける気温の変化 〃 其の二 寒威の影響 一三頁 其の三 気温の逆転 一八頁 第二款 気象 一九頁 其の一 風及風と気温との関係 二〇頁 其の二 氷霧 二一頁 其の三 積雪 二二頁 第三款 昼夜の時間及黎明薄暮 二二頁 其の一 昼夜の時間 〃 其の二 黎明及薄暮 二四頁 第四款 地表面の変化 二六頁 其の一 土地の凍結 二八頁 其の二 不凍土 三〇頁 其の三 野地坊主 三一頁 其の四 河川湖沼の結氷及解氷 三二頁 其の五 山地、森林 三五頁 其の六 市街、村落 三六頁 第五款 不毛 三六頁 第二節 耐寒装備 三九頁 第一款 防寒装傭 〃 其の一 個人の防寒装備、携行及著装法 〃 其の二 部隊の防寒装備 四二頁 第二款 給養装備 〃 第三款 給水装備 四三頁
- 作成年月日昭和27年9月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010014100
閲覧[規模]1
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-14(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]大東亜戦争 満洲関係 満洲に関する用兵的観察 第十三巻 昭二八、三 復員局資料整理課 満洲に関する用兵的観察 第十三巻 第五篇 極東ソ軍の戦略的特性に関する観察 昭和二十八年三月 復員局資料整理課
- 作成年月日昭和28年3月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010014500
閲覧[規模]44
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-14(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第二章 極東ソ軍の戦略配置に関する観察 極東ソ軍はその主力をもつて在満日本軍を大きく包囲していたその他の方面例へばカムチヤツカ半島や北樺太には僅かに歩兵約一ケ師団をそれ 配置していたにすぎないそして極東ソ軍主力の横腹にあたる日本海方面ほ潜水艦からなる太平洋艦隊が主としてその沿岸防備にあたつていた。このような姿が極東ソ軍の戦略配置にかんする基本的な骨組である。 第一節 兵力配置に関する変遷満洲事変勃発(一九三一年九月十八日)直後ごろソ軍はクラスノヤルスク以東に歩兵六箇師団、騎兵二箇旅団を配置していたにすぎない。時恰かも第一次五ヶ年計画時代であつたためソ連政府は対外的には協調政策を立前としていた。そして一九三一年十二月には日ソ不可侵条約の締結を提案しただが日本政府は約一年後にこの提案を拒否した。
- 作成年月日昭和28年3月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C13010014700
閲覧[規模]21
- [所蔵館における請求番号]満洲-全般-14(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第四章 一九四五年極東ソ軍の満洲作戦に関する観察 第二次世界大戦においてソ連当局が採つた戦争指導方針は先ず西方において独軍を繋滅ししかる後徐ろに対日戦に参加せんとするにあつたそれ故に対独作戦間日本にたいし努めて刺戟を与もぬようクレムリンが配慮したのはけだし当然だつたと云えよう。 ところが一九四四年十月米軍がフイリツビンに上陸してからソ連紙の対日論調は急に反日的となりだした。続いて同年の革命記念目前夜祭(十一月六日)においてスターリン首相は太平洋戦争以来はじめて日本を侵略国だと公然と誹謗した。これはソ連の対日態度の大きな変化と云えるつまりそのころからクレムリンは対日参戦のための前奏曲を奏し始めたのである。 第一節 兵力集中及作戦
- 作成年月日昭和28年3月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C14060414400
閲覧[規模]1
- [所蔵館における請求番号]南西-ビルマ-542(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]独立混成第二十四旅団戦史資料 昭和二十八年九月 復員局資料整理課
- 作成年月日昭和28年9月
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省 防衛研修所戰史室
No.
[レファレンスコード]C14060414500
閲覧[規模]5
- [所蔵館における請求番号]南西-ビルマ-542(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]「註」 本戦史資料は同旅団司令部に於て調製し留守業務部が整理せるものを整備複製したものである 目次 其の一 部隊履歴の概要 其の二 編成並に装備の概要 其の三 行動の概要 一 編成の経緯及編成完結 二 編成完結より九号作戦出動迄 三 九号作戦出動間 イ 出動部隊 ロ 残留部隊 四 九号作戦帰還よりメークテーラ会戦時頃迄 五 メークテーラ会戦時頃より終戦迄 六 終戦後 其の四 主要なる各時期に於ける作戦計画の骨子及兵力配備 一 編成当時 (昭一九、一) 二 九号作戦より帰還直後 (昭一九、一一) 三 メークテーラ会戦後 (昭二〇、六) 其の五 参加せる作戦(戦闘)経過の概要 其の六 作戦間に於ける人員の損耗 其の七 人員補充状況 其の八 作戦間の教訓
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C11111010600
閲覧[規模]2
- [所蔵館における請求番号]支那-支那事変北支-110(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]目次 一、第一軍作戦経過概要 二、附録 1、上奏案(現任支那駐屯車の状況)昭和十二年八月二十二日現任) 2、軍現下の情勢判断 3、対南方作戦構想 4、北支に於ける軍状況の概要 5、第一軍司令部職員戦時命課 6、方面軍司令官訓示 7、攻撃準備に関する第一軍命令 8、攻撃に関する第一軍命令 9、迫撃に関する第一軍命令 10、追撃統行(追撃目標延神)に関する第一軍命令 11、保定会議に対する兵站能力判断 12石家荘に向う追撃準備に関する第一軍命令 13、石家荘に向う追撃前進命令 14、石家荘攻撃の為の作戦計画 15、石勢荘攻撃準備に関する第一軍命令 16、勅語写 17、占領地の安定確保に関する方面軍
- 作成年月日昭和12年
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C11111010800
閲覧[規模]53
- [所蔵館における請求番号]支那-支那事変北支-110(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]第四章 太原攻略戦 一、軍は十月四日石家荘附近の敵陣地に対する攻撃命令に於て第二十師団は摩沱河々畔の敵を攻撃発会力なる一部を正大鉄道に沿ふ道路を太原方向に直率し可成速く議鉄道を確保せしむる如く部署せしが十月六日方面軍は第一軍に機を先せず一部を以て井経以西の高地に進出し敵の山西方面に対する直通を遮断すると共に爾後第五師団に策応せしむべき事を命令せり、第五師団は太原攻略の任務を有しあり 二、第二十師団の右諸支隊は摩沱河渡河攻撃後十月十三日井経を占領し其鯉登部隊は旧関に達せるも爾後優勢なる敵に対し戦況発展せざるものヽ如く第二十師団は十四日夜取敢へず歩兵一大隊山砲一中隊を石家荘附近に集結せる師団主力よ
- 作成年月日昭和12年
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省
No.
[レファレンスコード]C11111010900
閲覧件名2 附録(1)
[規模]48
- [所蔵館における請求番号]支那-支那事変北支-110(所蔵館:防衛省防衛研究所)
- [言語]日本語
- [内容]上奏案 講みて支那駐屯軍の現状に就て申上ます 支那駐砲軍は七月未北平附近支那第二十九軍を麿懲致しましか後平津地方の安定及交通線の確保を計り一方軍に増派されました第五第六及第十の各師団並其他の軍直轄部隊を北平を中心とする地区及天津附近の地区に集中して爾後の作戦を準備することを努めました、然るに北平附近天津附近其他に敗残兵の出没があり之等の掃蕩に腐心して居りました処支那 央軍の一部は迅速に察哈省に侵入し南口附近に拠りましたので八月中旬先づ独歩第十一旅団に之を攻撃せしめ次で逐次戦場に到着致しました第五師団を加へ鋭意之が力攻に勢めたので御座ります、一方第二十師団は主力を以て永定河右岸長辛店附近を確保し
- 作成年月日昭和12年
- 作成者復員局資料整理課
- 組織歴陸軍省